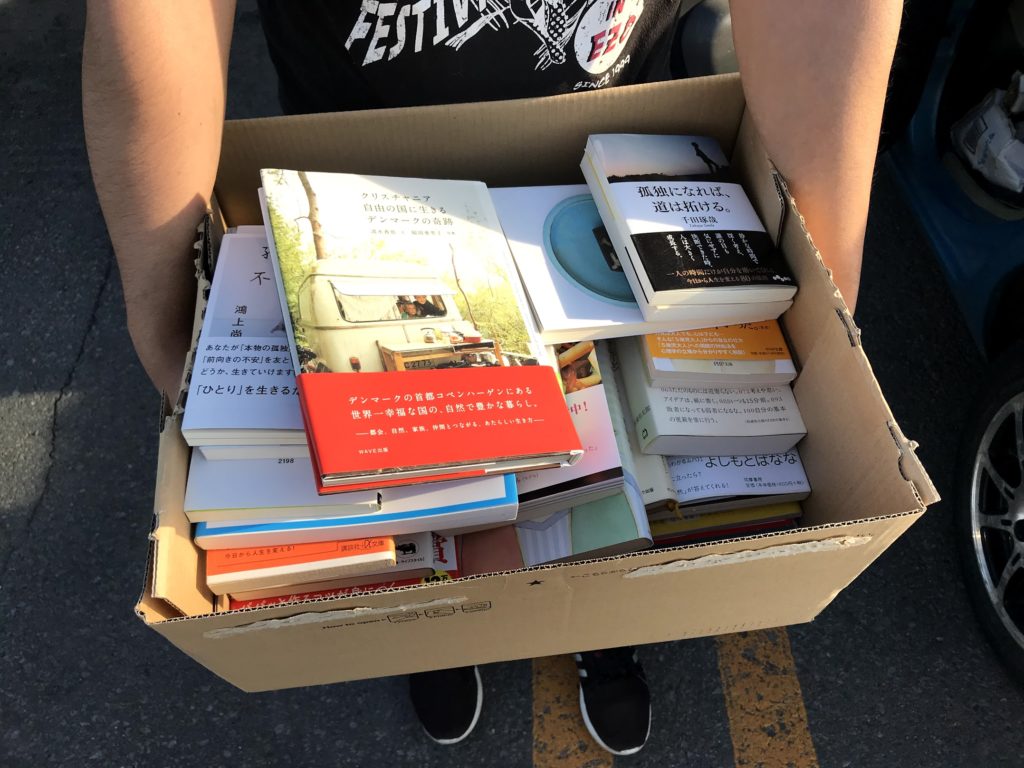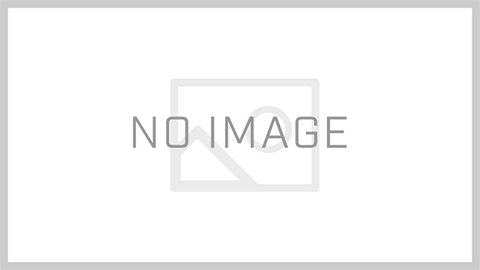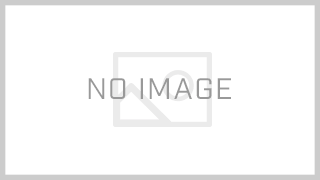久しぶりに食に関するドキュメンタリー映画を観ました。
映画「パパ、遺伝子組み換えってなあに?」の概要
タイトルの通り、パパであるジェレミー監督(アメリカ)が「遺伝子組み換えとは何か?体に悪影響があるのか?」の答えを追った、食のドキュメンタリー映画です。
ちなみに、こどもたちから質問されて探し始めたのではなく、子育てをする中で、わからないことが多く、その中でも気になったこととして「遺伝子組み換え」にフォーカスしたのが始まりです。
遺伝子組み換え作物とは?
WHOの説明は「自然界では起こりえないこと」という説明がある。
病気や害虫に強くなるように遺伝子操作された作物のことで、アメリカでは15年ほど前から遺伝子組み換えが政府によって認可されているのです。代表的な作物はトウモロコシ、大豆、じゃがいもです。
遺伝子組み換え作物を育てることにより、収穫量が上がり、飢餓に苦しむ国を救うために、開発されたとされています。
安全性についての調査研究は3ヶ月しかされていないのが実状です。遺伝子組み換えのタネを売っているモンサントやパイオニア社は有名ですね。
また、アメリカでは「遺伝子組み換え」の表示義務はなく、食のトレーサビリティもほとんどされていないため、本当の意味での「食の安全」を手に入れることは難しい。
▼遺伝子組換えしたタネを販売する巨大多国籍企業モンサントのことはこちらを
この映画で知りたかったこと
それはもちろん、「遺伝子組み換え」とは何か?に迫りたかったのです。
安全な食を求める一方で、「遺伝子組み換え」についての知識がなく、怪しいからという理由だけで、批判的にみるのはちがうと思ったし、近い将来子どもを育てる側として、必要な知識だと思ったためです。
知ってよかったこと、心配なこと
色々な食に関するドキュメンタリー映画を観てきた中で、遺伝子組み換えだけに的を絞った映画をみたので、私の中では色々な発見があったので、ここでいいことも、わるいことも紹介します。
いいことその1・ハイチ農民の勇気ある行動
2010年に起きた、ハイチの大震災の後、ハイチの農民がモンサントから遺伝子組み換えの種子を475トン寄贈されたが、タネを播かずに焼却処分したという。
西半球で一番貧しい国でもあり、大震災の後で、困っているはずなのに…わたしは一瞬戸惑ったが、理由はとても簡潔なものだった。それは…
「モンサントとの契約で、その年に収穫したものからのタネを次の年に播いてはいけないという契約があったから」と農民は話した。
もちろん、厳しい状況の中で、すべての農民がそうしたわけではなく、一部の農民はモンサントからタネを受けて農業をした人もいたのだ。しかし、その場所では作物が育たなくなり、お金も手元に残らなくなった。だからモンサントとの契約をやめて、「モンサントはNO!」という姿勢へと変わっていった。
いいことその2・ノルウェーでの遺伝子組み換えに関する教育
ノルウェーは国で遺伝子組換えの栽培も輸入も禁止しているので、学校で遺伝子組換えについて学ぶそうです。小さい頃からそういったことを学べる環境にあることが素敵!
お近くのヨーロッパ連合、EUでは遺伝子組み換えの表示を義務付けており、消費者が選択できるようになっているそうですが、ノルウェーはEUに加盟していないので、独自にこういうことができるようになっているのだと納得。
ちなみに、EUに加盟しない理由として、自国の独自性を守るため、農水産業を守るためというのがその理由とのこと。立派な国だな。
ちなみに、ノルウェーで販売されているハインツのケチャップはドイツで製造し、甘みには砂糖を使用しているそう。アメリカでは遺伝子組み換えのコーンシロップを甘みとして使用している。こうしたところでも企業は巧妙にマーケットを使い分けているというわけだ。
いいことその3・小さい子どもでもわかるGMのカラクリ
この映画の監督の長男は、「タネ」ヲタクです。タネに興味があり、いろんなタネのコレクターなのです。
なので、モンサントの「自家採種してはならない」という契約について、父からどう思うか質問されて、「そんなの絶対ヤダ、そんなところのタネを誰も買わなければ売れなくなるよ」と見事にモンサントのカラクリを見透かしていました。
小さい子でもわかることが、利害関係によって、大人は目をつぶらなきゃいけなくなってしまう。
心配なこと
心配その1・「世界をまかなう」という思想で工業化する農業
遺伝子組み換えの種子から作物を栽培している農家の主張は「食糧難を解決し、安定して食料を供給するための手段」としている。
だから、畑を拡大し、大量に栽培、収穫する、そのために大きな畑を所有し、大きな機械で農業をすることを目標としていた。
映画の中では、この栽培方法でなければ、大量に収穫する方法はないのか、という比較をしていた。とあるオーガニックファームによると、遺伝子組み換えの栽培での収穫量に差はなかったと発表した。
それなら、遺伝子組み換えである必要はないのだから、オーガニックが広まって欲しいと願う。
心配その2・除草剤を撒いても効かない「スーパー雑草・スーパー害虫」の出現
ここ数年でわかったことなのだが、除草剤が効かないスーパー雑草、殺虫剤が効かないスーパー害虫が出現しているという。
遺伝子組み換えはもともと、雑草や害虫に耐性のある遺伝子に組み換えているものなのだが、改良するにつれ、雑草や害虫も強くなってしまい、もう収集がつかなくなってきている。
遺伝子組み換え以外の作物への影響が心配だ。
心配その3・遺伝子組み換え作物による人体への影響
マウスでの2年に及ぶ実験を行ったフランス人の博士がいる。
実験では遺伝子組み換えの餌とそうでない餌を与えたところ、
メスマウス:腎臓と乳がん 80%が腫瘍
オスマウス:肝臓と腎臓の数値が悪い
という実験結果が出た。すべての原因がGMによるものではないが、その可能性は高いとしている。
ここで注目したいのは、「マウスの2年=人間の15年」だということ。遺伝子組み換えが認可されてから15年が経つので、人間に影響が出てくるのはこれからと言っても過言ではなさそう。
心配その4・多国籍企業が政治より権力を持つ恐ろしさ
モンサントなどの多国籍企業の恐ろしいところは、政府よりも力を持っているということ。市民が声を上げて、いくつかの州の法律を「遺伝子組み換え表示義務付け」に変えようとした。署名も十分集めて可決しそうになっても、モンサントの巨額マネーが動き、州を訴えようとしたため、否決になった州もあるという。
民主主義のはずが、市民が力を合わせても勝てないのは悲しい。
本日のまとめ
こういった情報は自分から調べないと手に入らないのが実状。
わたしはただ批判するのではなく、自分にできる行動を探すことが重要だと考えている。批判するのは簡単だけど、自分がどうその問題と向き合い、解決していくのかを考えていきたい。
自然ではないものは残らないと信じている。
おまけ1・今日からできること
・買い物の仕方を変える(遺伝子組み換え表示を見てお買い物をする)
・地産地消(地域の農家を支えよう)
・タネと農家を見つける(在来種栽培の、自分でも栽培してみる)
おまけ2・一筋の希望
そんなアメリカでも少しずつ変化が見えてきている。
・農家戸数の増加(大規模化に伴い減少が続いていたが、農家戸数が増加している=小さくても農業する人口が増えている)
・表示義務の法案が可決(遺伝子組み換え表示をする確約をするというホールフーズマーケットやいくつかの州が出てきた)
・ロシア・ペルーなどの国がアメリカの遺伝子組み換え作物の輸入を禁じた(買わない人が増えることこそが正しい方向へ進んでいくはず)